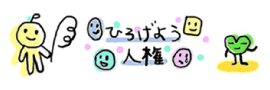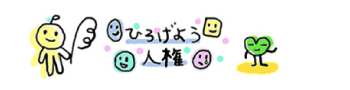谷川雅彦:部落差別解消推進法 成立の意義と活用への課題

プロフィール
谷川 雅彦(たにがわ まさひこ)
一般社団法人 部落解放・人権研究所 所長・研究部長
伊賀市人権政策審議会会長
世界人権宣言大阪連絡会議事務局長
一般社団法人 大阪府人権協会 理事
近畿大学非常勤講師
わが町にしなり子育てネット顧問

三度のチャンス
部落差別撤廃の重要なチャンスが過去、三度あった。最初のチャンスは1871年の「太政官布告」いわゆる「えた、非人の身分を今後、平民同様にする」とした「解放令」である。しかし「解放令」は身分制度を廃止したが、差別を解消しなかった。結果、部落差別は部落と見なされた土地と人間との関係を手がかりとして再編成された。二度目のチャンスは今から70年前の日本国憲法の施行である。日本国憲法は第十一条で「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とし、第十四条において「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」ことを明記した。しかし、「差別されない権利」を保障する法制度はまったくといっていいほど整備されてこなかった。結果、憲法に保障された基本的人権が差別によって奪われる「国民」が存在することになった。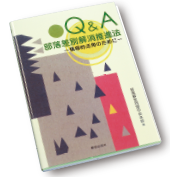
部落解放同盟中央本部 編集 解放出版社 発行
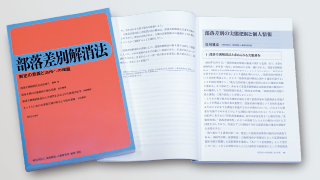
一般社団法人 部落解放・人権研究所 編集・発行
情報化社会と部落差別
総務省「平成28年度版情報通信白書」によると、2015年末のインターネット利用者数は、1億46万人(前年比0・3%増)、人口普及率は83・0%となっている。こうした中、かつて秘密裏に作成販売され、秘密裏に購入活用されていた「部落地名総鑑」がインターネットの中で公開され、インターネットに接続できる環境があれば誰もが閲覧できる状況にさらされている。インターネットは個人が匿名で簡単に情報発信ができて、拡散が容易であるという特徴を反映して、差別表現や内容が信じられないほどエスカレートしてきている。一方、子どもの結婚相手が部落出身者であった場合、「結婚させない」「結婚させたくない」が10・8%(2013年佐賀県人権に関する県民意識調査)、結婚にあたって相手が同和地区出身かどうかが「気になる」「気になった」が20・6%(2010年大阪府人権問題に関する府民調査)など、答申が「最後の越えがたき壁」と呼んだ結婚にあたっての差別意識は根強い。さらに同じ大阪府の調査で結婚にあたって相手の身元調査をすることが「問題ない」「どちらかと言えば問題ない」が37・2%にも及んでいることを考えるならインターネット上での被差別部落の所在地情報の流布といった事態が被差別部落出身者への差別を引き起こしているであろうことが容易に想像できる。
結婚などの差別被害を訴え出ることには被害者のカミングアウトを必要とするなど、そのハードルは高い。また差別する側も巧妙であり差別被害は表面化しにくい。
部落差別解消の四度目のチャンス
「答申」完全実施を求める国民運動をはじめ「部落解放基本法」制定要求国民運動、そして「人権侵害救済法」制定を求めた同和問題解決・人権政策確立要求国民運動につながる不断の取り組みと関係者の尽力によって、昨年「部落差別の解消の推進に関する法律」(以下、「部落差別解消推進法」)が成立、施行された。「部落差別解消推進法」は、部落差別が日本社会に存在すること、情報化社会の中で部落差別が深刻な状況にあること、こうした状況が施行70年を迎える日本国憲法に反していること、だからこそ部落差別の解消に取り組むことを法律に明記した。そして部落差別の実態調査の実施をふまえ、政府、自治体に部落差別解消のための施策を講ずることを求め、部落差別の相談体制の充実、部落差別の解消のための教育、啓発の実施を求めたのである。
部落差別の定義、禁止、救済、財政等についての規定が欠落しており、理念法にとどまっているという指摘があるが、「部落差別解消推進法」の具体化に取り組めば取り組むほど、これらの課題は解決されていかなければならないことになる。矛盾こそが発展の原動力となるのである。そして「部落差別解消推進法」は「特措法」のように時限立法ではなく恒久法である。かくして部落差別撤廃に四度目のチャンスがめぐってきた。
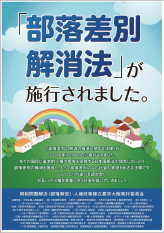
告知ポスター
部落差別の撤廃にむけた四度目のチャンスを徹底して活かしきる多様な取り組みが求められている。「部落差別解消推進法」は企画力が試される法律である。「特措法」のように事業実施の対象地域を指定する必要もないし、実施できる事業が決められているわけでもない。まさに部落差別の撤廃を求める本気度が私たちに試されているのである。
活用への課題
政府は「部落差別解消に関する施策」をどのようにすすめていくのか、「基本方針」と「総合計画」を策定するとともに、「総合計画」を推進していくための省庁横断的な「推進体制」を確立することが重要である。「基本方針」「総合計画」を策定するために「内閣同和対策審議会」のような当事者参加による審議機関を設置すること、「内閣同和対策審議会」が答申を出すにあたっての議論の前提になった「基礎調査」「精密調査」のような部落差別の実態調査を「部落差別解消推進法」第六条にもとづいて実施することが必要である。とりわけ、インターネット上での部落差別や発覚した部落差別事件の実態調査が急がれる。インターネット上で不動産購入や結婚・交際、採用・選考にあたってどのような部落差別行為やそれを助長する情報のやりとりがなされているのか、特徴的な事例をジャンルごとに収集することである。また地方公共団体の協力を得て、例えば過去10年間に発覚した部落差別事件を集約することである。こうした部落差別の具体的な事例にもとづき、部落差別がどのようにあらわれてきているのか、その特徴や差別性、問題点、背景要因、解決へ向けた課題を徹底して分析することである。
「部落差別解消推進法」具体化の取り組みを政府に求めていく上でも、法案を提出した自民党、公明党、民進党の国会議員、法案に賛同いただいた国会議員を中心に超党派の国会議員による「部落差別解消議員懇談会(仮称)」の結成が急がれる。こうした国会内での取り組みと、同和問題解決・人権政策確立要求国民運動中央実行委員会・都府県実行委員会が一体となって「部落差別解消推進法」を具体化する取り組みを強力にそして広範に展開することが求められる。 東京人権啓発企業連絡会に参加する企業においてもトップをはじめ新入社員にいたるまで部落差別の解消をめざす法律ができたことを知らせるとともに、引き続き、経営方針、社訓、行動指針などに差別禁止条項を盛り込むなど企業として部落差別の解消に取り組んでいることを社会に発信してほしい。
法律は制定されていないが、東洋経済「第12回CSR調査2017」によると、「LGBTへの基本方針(権利の尊重や差別の禁止など)」を持つ企業の割合は22・4%(207社)、作成予定が5・7%(53社)となっている。今や企業においてLGBT支援は必須の課題になっている。部落問題においてもぜひこうした企業風土を築き上げてほしい。東京人権啓発企業連絡会の担当者は部落問題の解決を、CSRにしっかりと位置づけ企業の「風土」となるよう社内で奮闘していただきたい。
「特措法」は事業実施を希望した被差別部落を対象としたいわば地方公共団体への財政支援法であった。しかし、「部落差別解消推進法」は部落差別を解消することを目的とした法律である。「特措法」は国で事業のメニューが決められた「靴に足を合わせる」法律であったが、「部落差別解消推進法」は部落差別の実態をふまえた部落差別の解消のための施策を講ずる「足に靴を合わせる」法律である。「部落差別解消推進法」は実態把握力、企画創造力、政策立案力が問われる法律なのである。また「特措法」は時限立法であったが「部落差別解消推進法」は恒久法であり、取り組めば取り組むほど成果があがる。そしてその出発点は部落差別の現実を可視化することである。法務省が「部落差別解消推進法」第六条をふまえた実態調査の実施にむけて有識者会議を発足させた。ここから取り組みがスタートするよう部落解放・人権研究所としても微力ではあるが全力で取り組みを進めていきたい。
部落差別の解消の推進に関する法律
(平成28年法律第百九号)(目的)第一条
この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第二条
部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条
国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに地 方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ず るよう努めるものとする。
(相談体制の充実)
第四条
国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。
(教育及び啓発)
第五条
国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。
(部落差別の実態に係る調査)
第六条
国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。
2018.3掲載